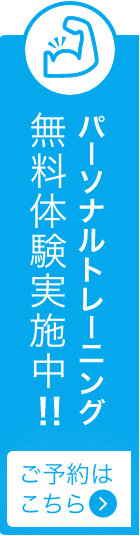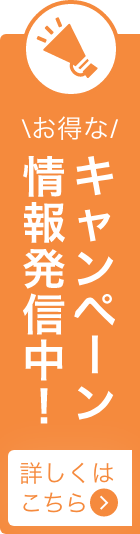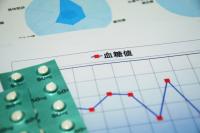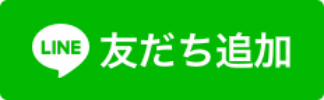薬に頼らない身体づくり。運動から始めよう!

2025/08/16 11:44 生活習慣病コラム
こんにちは。
浜松・豊橋市のパーソナルトレーニングジム
S-pace【エスペース】です。
生活習慣病や慢性疾患が増加する中、薬に頼ることが当たり前になってきています。
しかし、薬に依存した生活は副作用や臓器への負担、さらには経済的なコスト増加という問題を引き起こします。
こうした背景から、薬に頼らない健康づくりに注目が集まっています。
その中心にあるのが「運動」です。
今回は、運動がなぜ重要なのか、どのような効果があり、どのように始めるべきかご紹介いたします。
なぜ薬に頼らない身体を目指すのか

薬は症状を抑えるには有効ですが、根本的な解決にはならない場合もあります。
また、長期服用による副作用や薬物相互作用は無視できません。
健康寿命を延ばすためには、体の自然な調整機能を高める必要があります。
薬に依存するリスク:
・長期使用による臓器負担(肝臓・腎臓への影響)
・副作用による生活の質低下
・医療費負担の増加
薬に頼らない身体のメリット:
・免疫力や自然治癒力の向上
・メンタルヘルスの改善
・薬の管理や経済的負担からの解放
薬に頼るメリットとデメリット
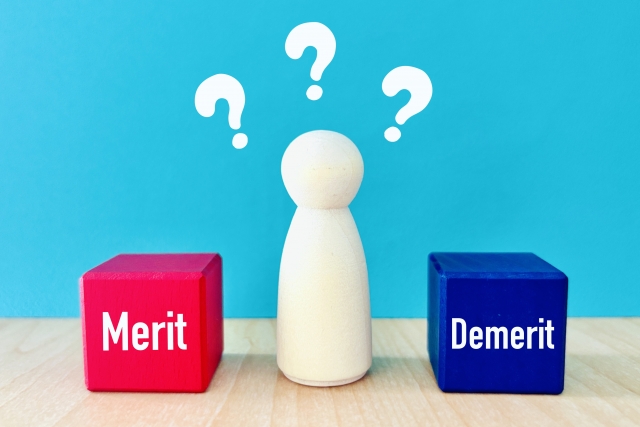
薬は現代医療において不可欠な存在ですが、その利用にはメリットとデメリットの両面があります。
薬に頼るメリット
1.即効性がある
薬は症状を迅速に緩和するため、急性症状や痛み、炎症のコントロールに効果的です。
例えば、抗生物質は感染症を短期間で改善し、命に関わる事態を防ぎます。
2.科学的根拠に基づく効果
薬は臨床試験を経て開発され、効果や安全性が確認されています。
そのため、適切に使用すれば信頼できる治療手段です。
3.生活の質を向上させる
慢性疾患を抱える人にとって、薬は症状をコントロールし、日常生活を維持するために重要です。
糖尿病、高血圧、喘息などの疾患では、薬による管理が不可欠です。
4.重篤な合併症を防ぐ
血圧降下薬や血糖降下薬は、心筋梗塞や脳卒中といった重大な疾患のリスクを下げる働きがあります。
適切な服用で命を守ることができるのです。
薬に頼るデメリット
1. 副作用のリスク
薬は体内で作用するため、副作用を避けることはできません。
胃腸障害や肝機能障害、アレルギー反応など、軽度から重篤なものまであります。
2. 長期服用による臓器負担
特に慢性疾患で薬を長期間服用する場合、肝臓や腎臓に負担がかかります。
これは薬物代謝や排泄の過程で避けられない現象です。
3. 薬物依存や耐性
鎮痛薬や睡眠薬などは、依存性や耐性を引き起こすリスクがあります。
使用をやめられなくなるケースもあり、注意が必要です。
4. 経済的負担
薬の服用は長期間になるほど医療費がかさみます。
特に高額な新薬や複数の薬を併用する場合、家計への影響が大きいです。
5.根本治療にはならない場合がある
薬は症状を抑えることが主な目的で、病気の根本原因を解決しないケースも多いです。
生活習慣病などは、生活習慣の改善を伴わなければ再発や悪化の可能性があります。
薬は現代医療において大きな役割を果たしていますが、副作用や依存、経済的な問題など、デメリットも存在します。
大切なのは「薬を正しく使うこと」と「薬に頼りすぎない生活習慣の構築」です。
特に慢性疾患では、運動や食事改善といったライフスタイルの見直しを組み合わせることで、
薬の量を減らし、より健康的な生活を実現できます。
運動の医学的エビデンス
運動は単なる体力維持ではなく、科学的に証明された「万能の薬」とも言える効果があります。
運動による効果は医学的観点から見て以下のような効果があります。
- 心血管疾患予防: 定期的な運動は心筋梗塞や脳卒中の発症率を30〜40%減少
- 糖代謝改善: 有酸素運動でインスリン感受性が向上、2型糖尿病の予防に寄与
- メンタルヘルス: 運動によりセロトニンやドーパミンが分泌され、うつ症状軽減に効果
さらに、週150分程度の中強度運動は死亡リスクを下げるとWHOも推奨しているのです。
運動がもたらす具体的メリット

・血圧の安定: 軽度高血圧で降圧効果が確認
・脂質異常改善: HDLコレステロールを増加させ、LDLを低下
・体重管理: 筋肉量増加で基礎代謝アップ
・ストレス解消: コルチゾール低下で精神的安定
今日から始められる運動習慣

有酸素運動:
- ウォーキング、サイクリングを1日30分、週5日
筋力トレーニング:
- 自重運動(スクワット、プランク)を週2〜3回
柔軟性とバランス:
- ヨガ、ストレッチを毎日5〜10分
ポイント:
- 無理をしない、段階的に負荷を上げる
- 持病がある場合は医師と相談
食事と睡眠で運動効果を高める
食事:
- 野菜、果物、魚を中心にバランスを意識
- 塩分・糖質・加工食品の摂取を控える
睡眠:
- 7〜8時間の質の高い睡眠を確保
- 寝る前のスマホ使用を控える
これらの生活習慣改善は、運動の効果をさらに高めます。
継続のための工夫
- スケジュールに運動時間を組み込む
- 小さな目標から始める(例:1日5000歩)
- 運動仲間やアプリを活用し、モチベーション維持
運動と薬の補完的な関係
薬が全く不要になるとは限りません。
しかし、運動習慣は薬の量を減らしたり、効果を高める補助的役割を果たします。
例えば、高血圧治療中の方でも、運動を継続することで降圧薬の減量が可能になるケースがあります。
運動不足が招くリスク

運動不足が招くリスク
運動不足は現代人にとって深刻な健康リスクであり、体と心に多くの悪影響を及ぼします。
- 肥満の増加:消費エネルギーが減少し、脂肪が蓄積しやすくなります。
- 生活習慣病の発症:インスリン抵抗性が進み、糖尿病や脂質異常症のリスクが高まります。
- 心血管疾患のリスク上昇:血流が悪化し、動脈硬化、心筋梗塞、脳梗塞の原因になります。
- 筋力と骨密度の低下:骨粗鬆症やサルコペニアを招き、転倒・骨折の危険が増加します。
- メンタルヘルスへの影響:ストレスが蓄積し、うつ病や不安障害の発症リスクを高めます。
これらの問題は、長期的に生活の質を大きく下げる要因となります。
日常生活に軽い運動を取り入れることで、こうしたリスクは大幅に軽減可能です。
さらに、長期間の座りっぱなしは心血管疾患やがんのリスクを上げるとされています。
現代人は平均で1日9時間以上を座位で過ごしているとされ、この習慣は「新しい喫煙」とも呼ばれているのです。
年齢別の運動アプローチ
- 20〜30代: 基礎代謝が高い時期に筋トレを取り入れ、将来の筋肉量維持を意識
- 40〜50代: ホルモンバランスの変化を考慮し、ウォーキングやヨガなど無理のない運動を習慣化
- 60代以降: 転倒予防のためのバランス運動と、軽めの筋トレが重要
まとめ
薬に頼らない身体をつくる第一歩は、運動です。
毎日の小さな積み重ねが将来の大きな健康資産になります。
焦らず無理なく始め、自分の体と対話しながら続けましょう。
それこそが、薬に頼らず健やかに生きるための最良の方法です。
運動は薬のように即効性はありませんが、長期的には心身の健康を支える大きな力となります。
適度な運動は、生活習慣病の予防や改善、メンタルヘルスの向上、骨や筋肉の健康維持など、
多岐にわたるメリットをもたらします。
さらに、質の高い睡眠やバランスの取れた食事と併せることで、薬に頼らない健康な体づくりが可能になります。
今からできる小さな一歩として、毎日の生活にウォーキングやストレッチを取り入れ、
体を動かす習慣をつけることをおすすめします。
無理のない目標を立て、少しずつ継続することが成功の鍵です。
最終的には、自分の体を自分で守れる力を身につけることが、真の健康につながります。
浜松市(鴨江・葵東)、豊橋市にあるS-paceでは経験豊富なパーソナルトレーナーがおります。
今回ご紹介したもの以外にも腰痛予防のお尻のストレッチや腹圧向上のトレーニング、
肩コリ予防の運動など様々な運動をご提供できます。
ご不安や、ご質問があればS-pace一同お待ちしておりますのでお気軽にご連絡ください。
==============================
お問い合わせ・無料体験の申込はこちら
◇浜松鴨江店
住所:浜松市中区鴨江3-73-20
TEL:053-570-5858
E-mail:s-pace1@sun-roots.com
Instagram:@s_pace.kamoe
◇浜松葵東店
住所:浜松市中区葵東1丁目11-23 1F
TEL:053-570-9147
E-mail:s-pace2@sun-roots.com
Instagram:@s_pace.aoihigashi
◇豊橋店
豊橋店HP:https://s-pace-toyohashi.com/
住所:愛知県豊橋市中浜町219-12
TEL:0532-26-8350
E-mail:s-pace-toyohashi@sun-roots.com
Instagram:@s_pace.toyohashi