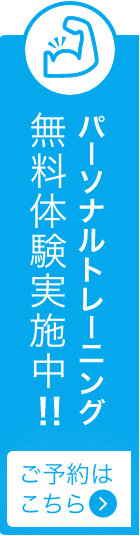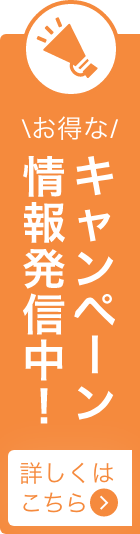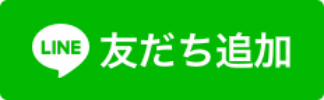長時間スマホを見てしまう人の 首・肩こりのサインと対策とは?

2025/05/10 13:24 トレーニングコラム
こんにちは。
浜松市・豊橋市のパーソナルトレーニングジム
S-pace【エスペース】です。
今回のコラムは、
「長時間スマホを見てしまう人の首・肩こりのサインと対策」
についてです。
現代の私たちの生活において、スマートフォンやタブレットは欠かせない存在です。
連絡手段としてはもちろん、ニュースのチェック、SNSの閲覧、動画視聴、ゲームなど、
多くの時間をスマホにどな費やしている人も多いでしょう。
最近では学校の授業でもタブレットを使って行うようになってきました。
しかし、そんな便利なスマホやタブレットが、体に悪影響を与えている可能性があることをご存じでしょうか。
特に、長時間スマホを見続けることで引き起こされる首や肩のこりは、多くの人が自覚していながらも、
その原因や対策を深く理解していないことが少なくありません。
今回はストレートネックの原因やメカニズムから医学的知識も含めその対策方法をご紹介いたします。
スマホが原因?首・肩こりのメカニズムとは

「ストレートネック」になっていませんか?
スマホを使っているとき、ついつい顔を下に向けた姿勢を長時間続けてしまうことが多いですよね。
この姿勢が続くと、首の自然な湾曲(カーブ)が失われ、「ストレートネック」と呼ばれる状態
になってしまうことがあります。
ストレートネックとは、本来であれば前方に緩やかにカーブしている頚椎がまっすぐになってしまう状態を指します。
この姿勢は首の筋肉に大きな負担をかけ、常に首や肩に緊張を強いるため、慢性的なこりや痛みの原因となるのです。
首・肩こりの原因となる他の要素
スマホ使用による不良姿勢は、単にストレートネックだけでなく、以下のような問題も引き起こします。
- 肩甲骨周りの血行不良:猫背の姿勢により肩甲骨が広がり、周辺の血流が悪化していく
- 眼精疲労:画面を長時間見続けることで目が疲れ、そこから首や肩の緊張へつながる
- 浅い呼吸:前かがみの姿勢が肺を圧迫し、酸素の供給が減少し、筋肉が疲労しやすくなる
首・肩こりのサインに気づこう

普段の生活の中で、以下のような症状がある場合、それは「首・肩こりのサイン」かもしれません。
- 首や肩にいつも違和感がある
- 頭痛が頻繁に起こる(特に後頭部)
- 腕や手にしびれがある
- 目の奥が重く感じる
- 朝起きたときからすでに首がだるい
- 集中力が続かない、イライラしやすい
これらの症状は、単なる「疲れ」ではなく、身体からのSOSであることが多いのです。
放置しておくと、慢性的な頭痛や肩こりだけでなく、自律神経の乱れ、睡眠の質の低下、
さらにはうつ状態にまでつながることもあるため、早めの対策が必要です。
医学的に見る首・肩こりの正体
筋肉の緊張とトリガーポイント
首・肩こりの主な原因は、筋肉の過緊張です。
とくに、首の後ろにある「僧帽筋(そうぼうきん)」や肩甲骨周辺の「肩甲挙筋(けんこうきょきん)」、
背中にかけて広がる「広背筋(こうはいきん」などが長時間収縮したままの状態になることで、
血流が悪化し、老廃物がたまりやすくなってしまうのです。
このような筋肉の疲労が進むと、「トリガーポイント」と呼ばれるしこりのような部位ができることがあります。
トリガーポイントは、押すと強い痛みを感じたり、離れた部位にまで痛みが放散したりする特徴があり、
慢性化しやすいのが特徴です。
神経への影響
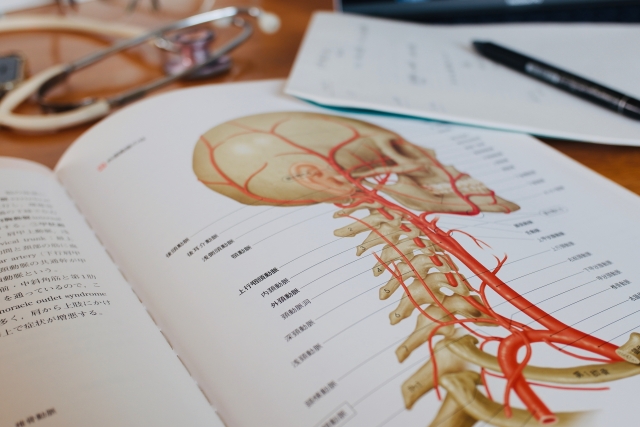
長時間のスマホ姿勢によって起こる首の不良姿勢は、首の骨(頚椎)の間から出ている神経根にも
影響を与えることがあります。
これが圧迫されると、単なる筋肉痛ではなく、「神経痛」のような症状が現れることもあります。
代表的な症状は以下のとおりです。
- 肩から腕、指先にかけてのしびれや痛みがある
- 力が入りにくい、ものがつかみにくい
- 焼けるような痛み(神経因性疼痛)がある
このような場合、単なるストレッチやマッサージでは改善しにくく、
整形外科での診断や治療、リハビリが必要になることもあります。
自律神経への影響
首には自律神経の働きと関係の深い交感神経幹が走っています。
不良姿勢や筋緊張によってこの部分が刺激されると、自律神経が乱れ、以下のような全身症状が現れることがあります。
- 頭痛・めまい
- 動悸・息切れ
- 不眠・寝つきの悪さ
- 胃腸の不調(便秘や下痢)
- 不安感やイライラ
つまり、スマホの見過ぎによる首・肩こりは、単なる筋肉の問題にとどまらず、
神経や自律神経、さらには全身のバランスにも悪影響を与える可能性があるのです。
このように、医学的な視点からもスマホによる姿勢の悪化や首・肩こりは見過ごせない問題になってくるのです。
症状が慢性化している方や、しびれや頭痛などを伴う場合は、早めに整形外科やリハビリテーション科、
神経内科などの医師に相談することをおすすめします。
さらに詳しい対策として、理学療法士による運動指導や、鍼灸治療・整体などの補完医療も、個人の状態に応じて取り入れると効果的です。
今すぐできる!首・肩こりを防ぐための対策
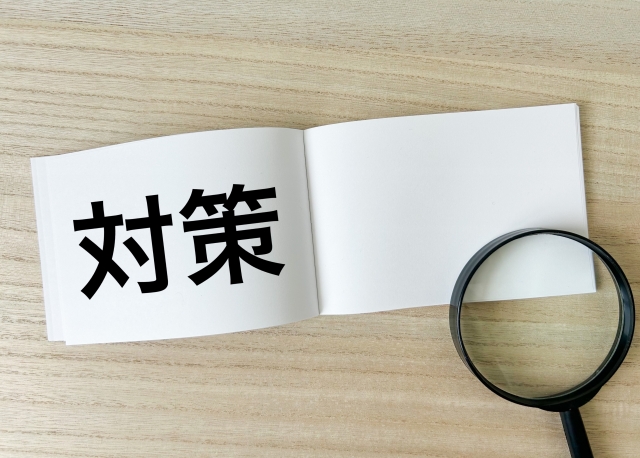
1. スマホの持ち方・見る角度を見直す
一番簡単で効果的なのは、スマホを「目の高さ」に持って見ることです。
顔を下に向けないように意識することで、首への負担を大きく減らすことができます。
【ポイント】
- スマホを見るときは、顔を下げるのではなく、スマホを持ち上げて見る
- スマホスタンドをうまく利用する
- 電車などでは膝の上にスマホを置かず、手で少し高い位置に保持するように
2. スマホ使用時間の制限・休憩の習慣化
集中していると、気づけば1時間、2時間とスマホを見続けてしまっていることもあります。
1時間に1回は意識的に休憩を取り、画面から目を離しましょう。
【ポイント】
- 20分に1回は遠くを見て目を休める(20-20-20ルール:20分に1回、20フィート先を20秒見る)
- タイマーアプリやスクリーンタイム機能で使用時間を管理する
- スマホを使わない時間帯を決める(例:寝る1時間前は使わない)
3. 簡単ストレッチ&エクササイズ
日々のちょっとしたストレッチでも、筋肉の緊張を和らげ、血行を改善することができます。
①首まわりのストレッチ
- ゆっくりと首を前後左右に倒し、30秒ずつキープする
- 首をゆっくり回す(左右それぞれ3回)
②肩甲骨エクササイズ
- 両肩を耳に向かってすくめてから一気にストンと落とす(10回)
- 肩を大きく回す(前・後ろに各10回)
- 両肘を背中側で近づけるように肩甲骨を寄せる(10秒×3回)
痛みが出る場合は無理せず中止してください。
4. 姿勢を改善する工夫
スマホだけでなく、デスクワークや食事中の姿勢も影響します。
普段から「正しい姿勢」を意識することが大切です。
【ポイント】
- 背筋を伸ばし、骨盤を立てる
- 椅子に深く座り、足裏は床につける
- パソコンやスマホは目線の高さに合わせる
5. 睡眠環境を整える
首・肩の筋肉をしっかり休めるためには、質の高い睡眠が欠かせません。
また、枕の高さや寝姿勢も、首のこりに大きく関係しています。
【ポイント】
- 首をしっかり支える枕を使う(高すぎず低すぎず)
- 横向きや仰向けで寝るようにする
- スマホを枕元に置かず、寝る直前は使用を控える
まとめ: 生活全体で「スマホ疲れ」を防ごう
現代人にとってスマホは切っても切れない存在ですが、便利である一方で、体には想像以上の負担がかかっています。
首や肩のこりを甘く見ず、日頃の習慣や姿勢を見直すことが大切です。
まずは「気づくこと」から始めてみましょう。自分のスマホの使い方、姿勢、日々の体の違和感に敏感になり、
少しずつ改善していくことで、首や肩の不調は確実に軽減されていきます。
今回ご紹介した対策や姿勢のポイントなども意識して過ごしてみてください。
浜松市(鴨江・葵東)、豊橋市にあるS-paceでは経験豊富なパーソナルトレーナーがおります。
今回ご紹介したもの以外にも腰痛予防のお尻のストレッチや腹圧向上のトレーニング、
肩コリ予防の運動など様々な運動をご提供できます。
ご不安や、ご質問があればS-pace一同お待ちしておりますのでお気軽にご連絡ください。
==============================
お問い合わせ・無料体験の申込はこちら
◇浜松鴨江店
住所:浜松市中区鴨江3-73-20
TEL:053-570-5858
E-mail:s-pace1@sun-roots.com
Instagram:@s_pace.kamoe
◇浜松葵東店
住所:浜松市中区葵東1丁目11-23 1F
TEL:053-570-9147
E-mail:s-pace2@sun-roots.com
Instagram:@s_pace.aoihigashi
◇豊橋店
豊橋店HP:https://s-pace-toyohashi.com/
住所:愛知県豊橋市中浜町219-12
TEL:0532-26-8350
E-mail:s-pace-toyohashi@sun-roots.com
Instagram:@s_pace.toyohashi