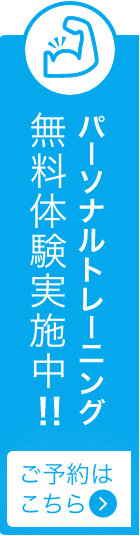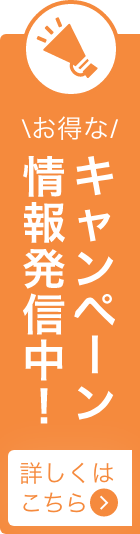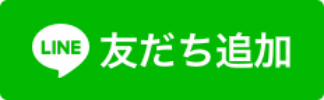なかなか体重が落ちない人の共通点とは?
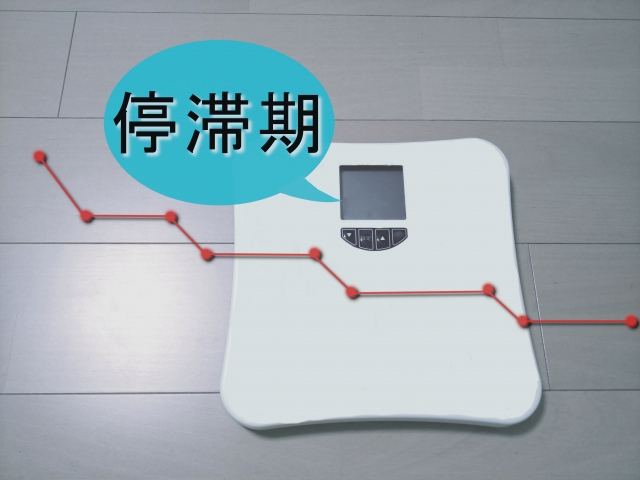
2025/08/23 15:03 トレーニングコラム
体重を減らしたいと努力しているにもかかわらず、思うように結果が出ないという
悩みを抱えている方は少なくありません。
体重が減らない原因は1つではなく、複数の要因が絡み合っていることが多いとされています。
今回は、「なかなか体重が落ちない人の共通点」について、詳しくご紹介いたします。
1. 摂取カロリーの過小評価
多くの方が自分の食事量を過小評価する傾向にあります。
食事を記録しない場合、人は実際よりも20〜30%程度少なく見積もることがあると報告されています。
例えば「野菜たっぷりのパスタだから低カロリー」と思っていても、ソースや油で高カロリーになることがあります。
主な原因
・間食のカウント漏れ
・飲料(ジュースやアルコール)の見落とし
・外食のカロリー計算の不正確さ
改善策
・食事記録アプリを活用することで、客観的なデータを把握できます。
・パッケージ表示を確認し、カロリーと栄養素を意識する。
・「一口ぐらいなら大丈夫」という意識を改め、摂取量を正確に記録する。
人は実際に食べた量を平均で30%低く見積もる傾向があると報告されています。
これが減量の妨げとなってしまうのです。
「これくらいなら…」が思ったよりも高いものだったりします。
2. 消費カロリーの過大評価
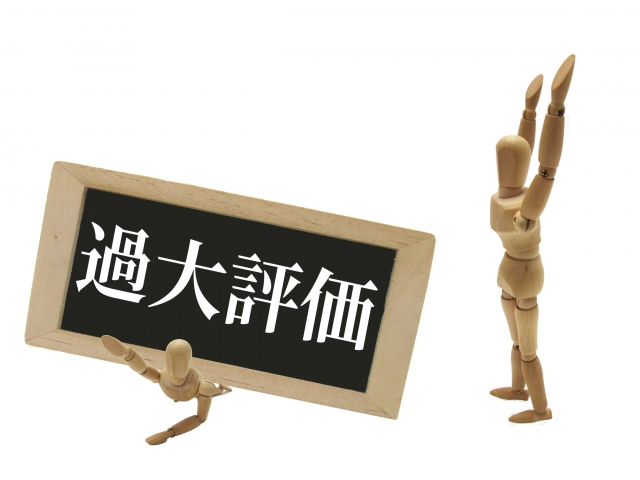
「運動をしたから大丈夫」と思い込み、必要以上に食べてしまうケースもよく見られます。
例えば、30分のウォーキングで消費するカロリーは約100〜150kcal程度であり、
菓子パン1個にも満たないことが多いのです。
そのため、ランニングや筋トレをしても、その消費カロリーは思ったほど大きくありません。
ポイント
・運動による消費カロリーは意外と少ないことを理解する。
・運動後の「ご褒美食べ過ぎ」を防ぐため、間食をヘルシーにする。
運動による体重減少効果は期待ほど大きくなく、食事管理との併用が必要とされています。
3. タンパク質不足
体重減少において、タンパク質は非常に重要になってきます。
タンパク質摂取が不足すると、筋肉量が減少し基礎代謝が低下します。
筋肉はカロリー消費の大きな要素であるため、減量中も筋肉を維持することが体重を落とすためには大切になります。
タンパク質の目安
・体重1kgあたり1.2〜2.0gを目安に摂取。
・鶏胸肉、魚、大豆製品などの高タンパク質食材を意識する。
高タンパク質食は満腹感を高め、総摂取カロリーを自然に減らす効果があるとされています。
4. 睡眠不足とストレス
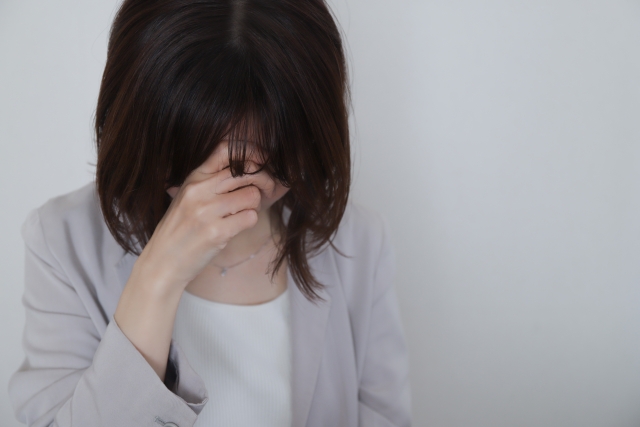
睡眠不足は食欲ホルモン(グレリン)の増加、満腹ホルモン(レプチン)の減少を引き起こし、
過食のリスクを高めます。
また、慢性的なストレスもコルチゾールの分泌を促進し、脂肪蓄積を助長します。
対策
・1日7〜8時間の睡眠を確保する。
・ストレス発散法(運動、瞑想、趣味の時間)を取り入れる。
睡眠時間が6時間未満の人は、食欲が増加し、肥満リスクが高まるとされています。
5. 水分摂取不足
水分不足は代謝の低下につながります。
体内の水分量は代謝反応に重要な役割を果たしており、脱水状態はエネルギー消費を抑制します。
水分摂取の目安
- 体重×30mlを目安に水分を摂取。
- 運動時はさらに追加補給を意識する。
ポイント:
・水をしっかり飲むことで、空腹感の軽減や代謝の維持につながります。
・少しでもいいので、30分に1回ぐらいでこまめに水分を摂るようにしましょう。
6. 無意識な活動の不足(NEATの低下)
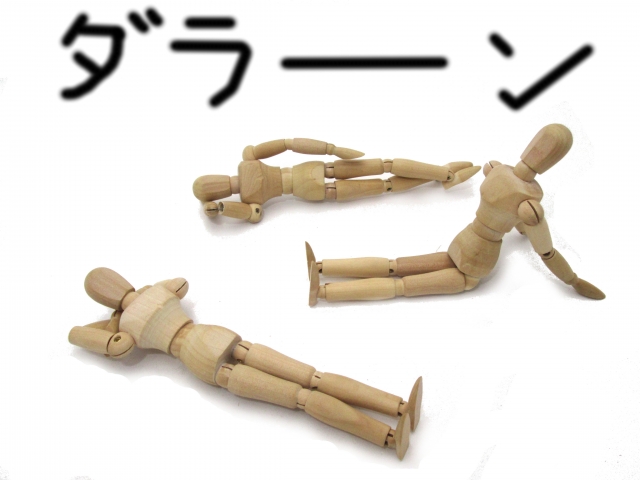
NEAT(非運動性熱産生)は、日常生活でのカロリー消費を指します。
デスクワーク中心の生活で、この活動が減少すると、体重減少が難しくなります。
具体的な工夫
・通勤で一駅分歩く。
・スタンディングデスクを活用する。
・家事や軽い運動をこまめに行う。
また、NEATを増やすことで、1日あたり100〜500kcal程度の差が生まれることもあります。
7. ホルモンバランスの乱れ
甲状腺機能低下症やインスリン抵抗性など、ホルモン異常は体重減少を妨げる原因となります。
特に40歳以降の女性では、更年期によるエストロゲン低下が代謝に影響します。
必要に応じて、医師による検査を受けたり、専門家に相談してみるのもおすすめです。
8. 停滞期のメカニズム
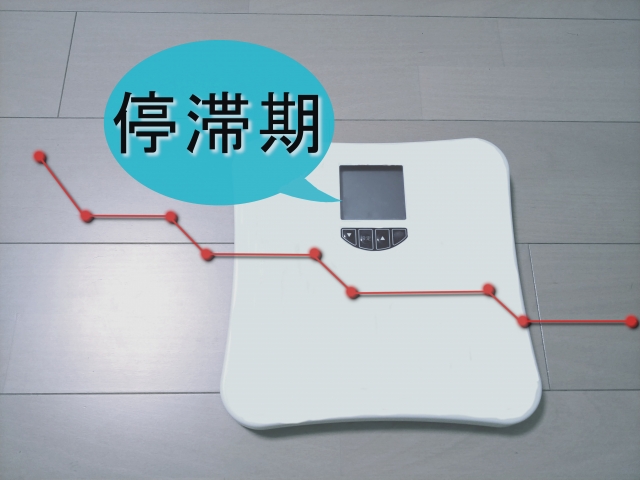
ダイエットを続けていると体重が減らなくなる「停滞期」が訪れます。
これは体が省エネモードに入り、基礎代謝を下げることでエネルギーを温存しようとする生理的反応です。
対応策
・カロリー制限を緩めてチートデイを設定する。
・運動強度を変化させる。
9. よくある誤解
ダイエットを行うに当たり以下のような誤解も多く見られます。
注意して行っていきましょう。
・「糖質を完全にカットすれば痩せる」→短期的には効果がありますが、リバウンドのリスクが高いです。
・「サプリだけで痩せられる」→科学的根拠は乏しく、食事と運動の基本が必要です。
体重を落とすための工夫
体重を減らすためには、ただ食事を減らすだけではなく、総合的なアプローチが重要です。
ここでは、効果的な工夫を詳しくご紹介します。
① 食事の質を改善する
体重を減らす際、食事の「質」に注目することは非常に重要です。
具体的な工夫
・低GI食品を選ぶ: 白米やパンを玄米や全粒粉に置き換え、血糖値の急上昇を防ぐ。
・野菜を先に食べる: 野菜を最初に摂取することで血糖コントロールを改善し、食べ過ぎを防ぐ。
・良質な脂質を適量摂取: オリーブオイル、ナッツ、魚に含まれるオメガ3脂肪酸は代謝に良い影響を与える。
ポイント: 加工食品や糖質の多いお菓子、飲料を避け、自然な食材を中心にすることが大切です。
②食事タイミングの最適化
近年の研究では、同じカロリーを摂っても、食べる時間帯によって脂肪の蓄積や消費が変わることが分かっています。
具体的な工夫
・朝食をしっかり摂り、夕食を軽めにする。
・夜遅い食事を避け、就寝3時間前までに食事を終える。
時間栄養学の観点から、昼間の代謝が活発な時間にエネルギーを摂取する方が、肥満予防に効果的です。
③スマートな間食術
間食を完全にやめる必要はありませんが、内容とタイミングを工夫することで減量に役立てられます。
おすすめの間食
・無糖ヨーグルト+ベリー類
・ナッツ(素焼き・無塩)
・プロテインシェイク
注意点: 間食のカロリーは1日100〜150kcal程度に抑えることを意識しましょう。
④運動を生活に取り入れる
運動は単なるカロリー消費ではなく、基礎代謝を高め、ホルモンバランスを整える役割も果たします。
おすすめの運動
・有酸素運動: ウォーキング、ジョギング、水泳を週150分以上。
・筋力トレーニング: 大筋群(スクワット、デッドリフトなど)を中心に週2〜3回。
運動のコツ
運動は完璧を目指すのではなく、まずは「毎日10分歩く」など継続可能な習慣にすることが大切です。
⑤食べ過ぎを防ぐための心理的工夫
体重管理において、心理面の影響は大きく関わってきます。
食べ過ぎを防ぐ工夫
・ゆっくり食べる(1口20回以上噛む)
・食事前にコップ1杯の水を飲む
・「ながら食べ」を避け、食事に集中する
人の身体は満腹感を感じるまでには約20分かかるため、早食いを防ぐことが食べ過ぎ防止につながります。
⑥習慣化と小さな目標設定
ダイエットを成功させるには、短期間での結果を求めず、生活習慣を徐々に改善することが不可欠です。
目標設定の方法
・毎週1つずつ新しい習慣を追加する(例:朝に500mlの水を飲む)。
・体重ではなく行動を目標にする(例:「今週は3回ウォーキング」)。
習慣化には平均66日かかるとされるため、焦らず少しずつ取り組むことがポイントです。
まとめ
体重がなかなか落ちない背景には、生活習慣、食事内容、心理的要因、ホルモンの影響など、
複数の要因が絡み合っています。
そのため、体重を落とすためには、食事・運動・心理面・生活習慣すべてに
バランスよくアプローチすることが重要です。
小さな工夫を積み重ねることで、大きな結果につながります。
自己判断だけでなく、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることも大切です。
正しい知識と継続的な取り組みで、無理のない健康的な減量を目指しましょう。
浜松市(鴨江・葵東)、豊橋市にあるS-paceでは経験豊富なパーソナルトレーナーがおります。
今回ご紹介したもの以外にも腰痛予防のお尻のストレッチや腹圧向上のトレーニング、
肩コリ予防の運動など様々な運動をご提供できます。
ご不安や、ご質問があればS-pace一同お待ちしておりますのでお気軽にご連絡ください。
==============================
お問い合わせ・無料体験の申込はこちら
◇浜松鴨江店
住所:浜松市中区鴨江3-73-20
TEL:053-570-5858
E-mail:s-pace1@sun-roots.com
Instagram:@s_pace.kamoe
◇浜松葵東店
住所:浜松市中区葵東1丁目11-23 1F
TEL:053-570-9147
E-mail:s-pace2@sun-roots.com
Instagram:@s_pace.aoihigashi
◇豊橋店
豊橋店HP:https://s-pace-toyohashi.com/
住所:愛知県豊橋市中浜町219-12
TEL:0532-26-8350
E-mail:s-pace-toyohashi@sun-roots.com
Instagram:@s_pace.toyohashi