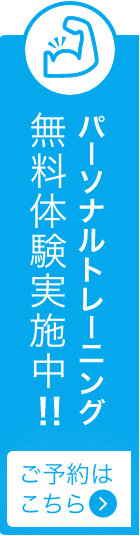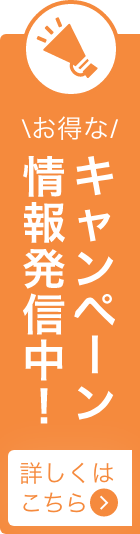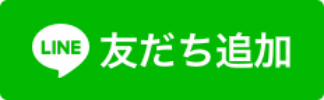膝や足首が痛くなる人の特徴と対策−歩く前にチェックすべき「土台」の重要性とは?

2025/11/11 16:25 トレーニングコラム
こんにちは。
浜松市・豊橋市のパーソナルトレーニングジム
S-pace【エスペース】です。
「歩き始めや、少し長く歩くと膝や足首が痛む」「最近、階段の上り下りがつらい」と感じていませんか?
膝や足首の痛みは、年齢を重ねるにつれて多くの人が経験する不調ですが、
その原因は「年のせい」と片付けられるものではありません。
むしろ、日々の「歩き方」や「体の使い方」といった習慣に潜む小さな歪みや負担の積み重ねが、
関節という体の土台に過剰なストレスを与え続けている結果です。
特に膝関節と足首関節は、全身の体重を支え、歩行時の衝撃を吸収する非常に重要な役割を担っています。
これらの関節に痛みが出る方の多くには、共通する身体的な特徴や、見過ごされがちなチェックポイントが存在します。
本稿では、膝や足首の痛みに悩む方の特徴を医学的な観点から分析し、痛みを予防・軽減するために、
日々の生活や歩行前に必ずチェックすべき重要なポイントを詳しく解説いたします。
膝や足首が痛くなる人に共通する3つの特徴

痛みは、突然現れるものではありません。
長期間にわたって関節に負担をかけ続けた結果として発症します。
痛みが出やすい人には、いくつかの共通した身体的・習慣的な特徴があります。
1. アライメント(骨の並び)の異常
膝や足首の痛みの多くは、関節そのものの変性(変形性膝関節症など)だけでなく、
骨の並び(アライメント)の異常によって引き起こされる「代償動作」に起因します。
・O脚・X脚の傾向:
O脚(内反膝): 膝が外側に湾曲し、膝の内側に過度な負担がかかりやすくなります。
X脚(外反膝): 膝が内側に入り込み、膝の外側や足首の内側に負担が集中しやすくなります。
・扁平足(へんぺいそく): 土踏まずがなくなり、足裏のアーチ構造が崩れている状態です。
このアーチは、着地時の衝撃を吸収する天然のクッションの役割を果たしています。
扁平足になると、衝撃吸収機能が失われ、その衝撃が直接、足首、膝、さらには腰へと伝わり、
関節にダメージを与えます。
・過回内(オーバープロネーション): 歩行時に足首が内側に倒れ込みすぎる状態です。
これが続くと、膝関節が内側にねじれるストレスを受け、膝の外側や内側の組織を損傷しやすくなります。
2. 筋肉のアンバランスと柔軟性の低下
関節は、周囲の筋肉によって支えられ、安定性を保っています。
この筋肉のバランスが崩れると、関節は不安定になり、特定の部位に摩擦や負荷が集中します。
・大腿四頭筋(太もも前)の弱化: 膝を伸ばす際に使う筋肉で、特に内側広筋の弱化は、
膝関節を安定させる力を失わせ、膝蓋骨(膝のお皿)が正常な位置からずれやすくなる原因となります。
・殿筋群(お尻の筋肉)の機能不全: お尻の筋肉は、歩行時に骨盤の安定性を保ち、
股関節が内側にねじれるのを防ぐ重要な役割を担っています。
この筋肉が弱いと、歩くたびに体がブレたり、膝が内側に入ったり(ニーイン)、足首にねじれの負担がかかったりします。
・ハムストリングス(太もも裏)の硬さ: 太もも裏の筋肉が硬いと、歩行時に股関節や膝の動きを制限し、
膝関節に過度な伸展ストレス(過度に伸ばされる力)をかけやすくなります。
3. 誤った歩行習慣と生活習慣
関節への負担は、日常の何気ない動作の中に潜んでいます。
・「ドタドタ歩き」: 着地の衝撃を足や膝で吸収せず、かかとから強く地面に打ち付けるような歩き方です。
本来、足首や足裏のアーチが吸収すべき衝撃が、直接膝関節へと伝わります。
・猫背・反り腰: 姿勢の崩れは、重心の位置をずらし、膝や足首に不均等な負担をかけます。
特に猫背は、体重が前方に移動し、膝関節の曲げ伸ばしのバランスを崩しやすくなります。
・体重の増加: 体重が1kg増えるごとに、歩行時にはその約3〜7倍の負荷が膝にかかると言われています。
体重の増加は、関節への物理的なストレスを劇的に高めます。
痛みを防ぐ!歩く前にチェックすべき5つのポイント

膝や足首の痛みを予防し、安全に歩くためには、意識的に自分の体の「土台」と「使い方」をチェックすることが
不可欠です。
歩行を始める前に、以下の5つのポイントを確認しましょう。
チェック1:足裏のアーチの機能(扁平足の有無)
足裏のアーチが機能しているかどうかは、衝撃吸収の生命線です。
・確認方法: 立ち上がった際、足の内側(土踏まず)に隙間があるかを確認します。
隙間がない場合は扁平足の可能性があります。
・対策:
インソールの活用: 自分の足の形に合ったオーダーメイドまたは既製品のインソール(中敷き)を使用し、
失われたアーチをサポートすることで、膝や足首への負担を軽減できます。
タオルギャザー: 床に敷いたタオルを足の指だけで手繰り寄せる運動を行い、足裏の筋肉(足底筋)を鍛えましょう。
チェック2:足首の柔軟性(背屈・底屈)
足首の可動域が狭いと、歩行時に膝や股関節でその不足分を補おうとするため、代償動作が生まれます。
・確認方法: 壁に向かって立ち、つま先を壁につけたまま、膝を壁に向かって曲げます。
このとき、かかとが浮かないか確認します。かかとが浮く場合、足首の柔軟性が低下しています。
・対策:
アキレス腱ストレッチ: 足首周りの筋肉(特にふくらはぎ)を丁寧にストレッチし、可動域を広げましょう。
チェック3:片足立ちの安定性(殿筋群の機能)
片足でしっかりと立てるかどうかは、歩行時の体の安定性、特に殿筋群の機能を示します。
・確認方法: 壁などに頼らず、片足で5秒以上立てるかチェックします。
このとき、体が大きくブレたり、軸足の膝が内側に入ったりしないか確認します(ニーインのチェック)。
・対策:股関節周りの筋トレ: 横向きに寝て股関節を開閉する運動(サイドレイズ)や、
ブリッジ運動(ヒップリフト)を行い、殿筋群(特に中殿筋)を強化しましょう。
チェック4:靴の状態と選び方
普段履いている靴が、関節の痛みを引き起こしている可能性があります。
・確認すべき点:
かかとのすり減り: 靴底の特定の部分だけが異常にすり減っている場合、
それはあなたの歩き方やアライメントに大きな歪みがあることを示しています。
靴のフィット感: 足の指が圧迫されていないか、かかとがしっかり固定されているかを確認します。
・対策:
クッション性と安定性のある靴: 着地時の衝撃を吸収するクッション性があり、
かつ足首を安定させるホールド感のある靴を選びましょう。
ハイヒールや底の薄い靴は避けるべきです。
チェック5:膝関節の「ねじれ」の有無
歩くとき、膝と足先が同じ方向を向いているかを確認します。
・確認方法: 鏡の前で立ち、膝の皿(膝蓋骨)と足先の向きをチェックします。
膝は正面を向いているのに、足先が外側を向いている、またはその逆の場合、
歩行時に膝が不自然なねじれを受けている可能性があります。
・対策:
内転筋の強化: 太ももの内側の筋肉が弱いと、膝が外に開きやすくなります。
内ももにボールを挟んで締める運動などで内転筋を鍛え、膝の安定性を高めましょう。
まとめ:体を整え、歩く喜びを再認識する
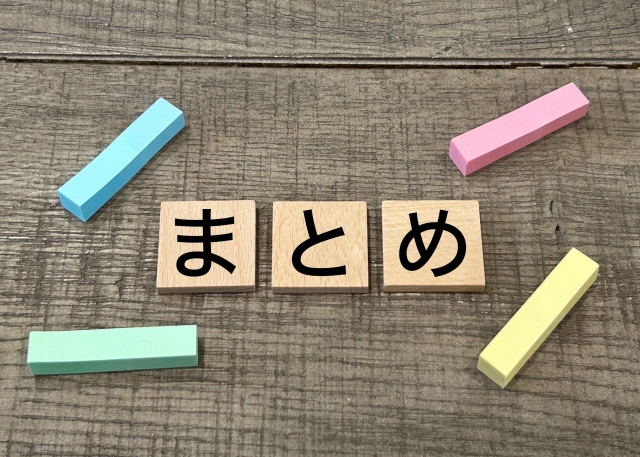
膝や足首の痛みは、あなたの体の「土台」が悲鳴を上げているサインです。
その特徴は、アライメントの崩れ、筋肉のアンバランス、誤った歩行習慣に集約されます。
痛みを「年のせい」と諦めるのではなく、
・足裏のアーチと足首の柔軟性を取り戻し、
・お尻周りの筋肉を強化し、
・正しい靴を選び、
歩行前にこれらのチェックを行うことで、関節にかかる不必要なストレスを大きく軽減できます。
もし痛みが続く場合は、自己判断せず、必ず整形外科医や理学療法士などの専門家に相談し、
正確な診断とリハビリテーションを受けることが重要です。
体の土台を整え、正しい体の使い方を意識することで、再び軽やかに歩き、人生の質を高めることができるでしょう。
浜松市(鴨江・葵東)、豊橋市にあるS-paceでは経験豊富なパーソナルトレーナーがおります。
今回ご紹介したもの以外にも腰痛予防のお尻のストレッチや腹圧向上のトレーニング、
肩コリ予防の運動など様々な運動をご提供できます。
ご不安や、ご質問があればS-pace一同お待ちしておりますのでお気軽にご連絡ください。
==============================
お問い合わせ・無料体験の申込はこちら
◇浜松鴨江店
住所:浜松市中区鴨江3-73-20
TEL:053-570-5858
E-mail:s-pace1@sun-roots.com
Instagram:@s_pace.kamoe
◇浜松葵東店
住所:浜松市中区葵東1丁目11-23 1F
TEL:053-570-9147
E-mail:s-pace2@sun-roots.com
Instagram:@s_pace.aoihigashi
◇豊橋店
豊橋店HP:https://s-pace-toyohashi.com/
住所:愛知県豊橋市中浜町219-12
TEL:0532-26-8350
E-mail:s-pace-toyohashi@sun-roots.com
Instagram:@s_pace.toyohashi